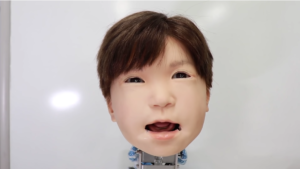フィンランドの科学者たちがプラスチックの小片に光に反応して動くことを教えました。動きはプラスチックが異なる刺激を関連づけさせることによって起こると言います。

この取り組みは有名なパヴロフの犬の実験からヒントを得たものであり、生物界と物質界の境目を曖昧にする研究です。しかし、プラスチックが既に世界を占領しつつあると懸念している人々にとって、これは悪夢が現実化に向かっているように見えます。
タンペレ大学のアリ・プリーメアイ教授が実験しているプラスチックはペットボトル用のプラスチックよりはるかに高機能なものです。染料でコーティングした熱応答性の液晶ポリマー・ネットワークから作られており、熱エネルギーを運動エネルギーに変換することができます。
当初、プラスチックは熱には反応するものの、光などのエネルギー形態には無反応でした。しかし、科学誌「Matter」で発表された同教授と共同研究者たちの論文によると、パヴロフの例に倣い、この高機能プラスチックの小片が光と熱を関連づけるように条件づけをしたということです。
パヴロフは犬たちにベルとエサを関連づけるように教え、最終的にはベルの音のみで犬たちは唾液を出すようになりました。これと同様に、プリーメアイ教授がプラスチックの小片に熱と光を同時に当てた後、プラスチックは光のみで熱を当てた時と同じ反応を示すようになりました。
条件づけられたプラスチックの小片は光が当たると丸まり、暗闇では平らに戻ります。プラスチックを適切な形状にすることで、丸まったり、平らに伸びたりするのをただ同じ場所に留まらせるのではなく、前進する運動に変換させることができます。
研究チームはこれを「歩行」と表現していますが、むしろ、シャクトリムシの進み方に似ています。現在可能なスピードは秒速約1ミリメートルなので、このような物質が人より速く進むことを今のところは心配しなくても良いようです。しかし、海洋プラスチックごみを減らす活動がまもなく新たな課題に直面することになるかもしれません。
論文の共著者であるアールト大学のオリ・イッカラ教授が、物質は学習することが可能かということに思いを巡らせた際にこの研究は始まりました。
コンピュータは学習することが可能だと私たちは知っています。でも、もっと単純な物ではどうでしょうか。以前、同じ研究チームが行った研究で、ゲル(ゼリー状のコロイド溶液)が光に当たると溶けるように条件づけることに成功したので、単純な物質も学習する可能性があることが証明されました。
この最新の論文では、プラスチック、すなわち、内部の分子の相対的な位置取りによって柔軟性が変わる物質について調べています。「物質が学習するためにはその物質に記憶する力がなくてはなりません。物質が加熱された時、事前に液晶ポリマーの表面に塗ってあった染料が物質の中に沁みていき、これが記憶の形成に相当します」と同教授は述べています。
研究チームは物体をつかむことさえプラスチックに学ばせました。さらに、狭い波長域に反応する染料を利用して、特定の光の色に反応を調整するプラスチックを開発する計画があります。
成功すれば、非常に軽いロボットを製作することができるようになります。そのロボットは動力供給装置を装備する必要がなくなり、代わりに離れたところから光を使って制御することになります。
プリーメアイ教授は、パヴロフの犬の条件反射と似ていると言うのは、生物学的なものに比べてプラスチックの動きが単純なシステムであることを考えれば誇張表現だと批判されるかもしれないと認めています。けれども、今回の研究はさらに複雑なシステムを導入するための足掛かりとなると見ています。
reference: IFLscience