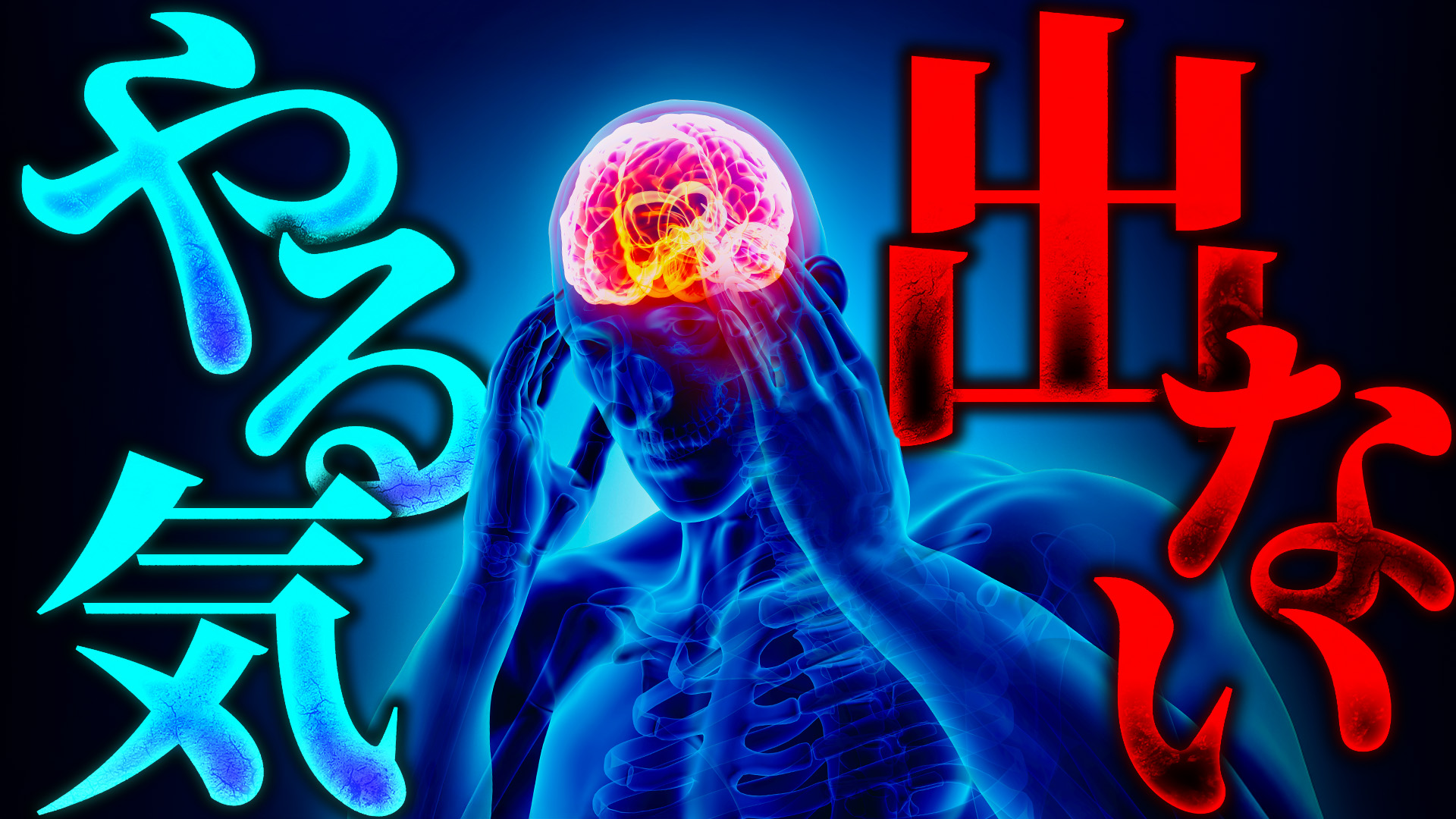今や、現代社会になくてはならない移動方法である航空機。
その運行数は年々、増え続けています。2019年だけでも約4,000万件の航空便が運行しており、単純な平均をとれば1日あたり10万件以上の航空機が飛行しているということになります。
これだけのフライト数があるということは、便利で安全性が高いということの裏返しでもありますが、やはり事故発生率をゼロにするというのは非常に困難です。
年々、企業努力や技術革新によって事故数は減っていますが、それでも直近の10年間だけでも50件近い航空機事故が発生しています。
航空機事故と一言に言っても、離陸時や上昇時、下降時や着陸時など飛行フェイズによって被害の大きさに傾向があります。そのフェーズの中で、特に事故が大きくなりやすいのが、飛行機が最も高い高度を飛行している時に起こる事故です。
航空機事故情報を取り扱うPlaneCrashInfo(プレーンクラッシュインフォ)が報告した1950年代から2010年代の航空事故の統計によると、飛行機がもっとも安定して飛行できる高度1万メートル前後を飛行しているときに事故が起こる確率は、事故全体の16%。そのうちの約半分が死亡事故に繋がると言われています。
中には、生きたまま空中に放り出されるというゾッとするようなケースもあるようです。もし、パラシュートもつけずに高度1万メートルに放り出されたらどうなるのでしょうか?生き残ることはできるのでしょうか?
今回は、飛行中の旅客機から落下するとどうなるのかについてご紹介したいと思います。
1972年1月26日、チェコスロバキア上空を飛行していたJAT367便は、高度1万メートルでバラバラに空中分解してしまいました。チェコスロバキアの調査委員会による公式記録では、事故の原因がコンパートメント部に設置された爆弾の爆発によるものだと報告されています。
同機には乗員6名と乗客22名が搭乗していましたが、およそ10,000メートルの巡航高度での空中分解だったため、事故発生当初の生存者は絶望視されていました。
しかし、客室乗務員として働いていたヴェスナ・ヴロヴィッチは、ただ一人生還を果たします。なぜ彼女だけが助かることができたのか。それはいくつもの幸運が重なったことによるものでした。
爆発発生直後、彼女は分解した航空機の中に閉じ込められ、その残骸は木の葉が舞い降りるように落下したため、落下のスピードを和らげることができたと考えられています。
また、山の斜面にある木々を滑るように着地したために、生存可能な衝撃で済んだというのです。
とはいえ彼女は、頭蓋骨1か所、脚2か所、椎骨3か所を骨折する重症でした。それでも生存できたのは、墜落から45分後には救助隊に発見され、即座に輸血を受けたことで、出血多量による死を免れることができたからです。
この奇跡の生還を果たしたヴェスナ・ヴロヴィッチは「パラシュートなしで落下して生還を果たした世界記録保持者」としてギネス記録にも認定されています。
彼女は事故の後、一時は腰から下が麻痺していましたが、手術後に回復し、JAT航空でデスクワークや飛行勤務にも従事しました。これだけ衝撃的な出来事があったのにも関わらず飛行勤務まで可能だったのは、「衝突の記憶がないためだ」と彼女自身が説明しています。
それでは、高度1万mから落下した彼女の身に何が起こったのか詳細にご紹介しましょう。そこのあなた、実験台です。
まず初めに、彼女が置かれた環境を考えて行く必要があります。そもそも、なぜ飛行機は高度1万メートルを飛行するのでしょうか?それは空気の密度と関係があります。地上と比べ高度1万メートルは空気密度が比較的小さい空間です。
そのため、空気抵抗を受けにくく、少ない燃料で速度を維持しやすいのです。一方で、エンジンが推進力を生むためには、燃料を燃焼させる酸素が必須です。この酸素の密度は高度が上がるにつれて小さくなって行きます。
つまり、空気抵抗を受けにくく、エンジンが推進力を生むために必要な酸素を確保できるちょうどいい高さが1万メートルなのです。この高度1万メートルでは気圧が0.26気圧と地上の1/4程度。
人間が生存できないほど酸素濃度が低い高所の領域と呼ばれるデスゾーンでも8,000メートルほどだということを考えると、いかに過酷な環境かが分かるでしょう。さらに、外気温は-50度と超極寒です。
ここに放り出されると、人間は酸素濃度が足りず、即座に低酸素症に陥り意識を失います。ヴェスナ・ヴロヴィッチは爆発による衝撃で意識を失った可能性もありますが、いずれにしても意識を保つことはありませんでした。
また、彼女の場合は、運よく飛行機の残骸に閉じ込められる形で落下し始めましたが、機体外に放り出された場合には、重力に引かれてどんどん加速していきます。
空気密度も小さいため、例えば高層ビルから飛び降りた場合より加速度は大きくなります。ある程度加速すると空気抵抗が大きくなり、加速は止まります。
とはいえ意識を失っている状態で、頭を下にして落下していると仮定すると、空気抵抗と加速が釣り合っている速度は時速300キロメートルにもなります。
この時、地上までの猶予はおよそ3分。
さらに落ち続け、高度が約6,700メートルになると、酸素濃度が徐々に高くなり、運が良ければ失っていた意識が回復します。ヴェスナ・ヴロヴィッチは事故後に「記憶がない」と説明しているため、ここでは意識が回復しなかったようです。
もし、意識が戻った場合には、ここで垂直に落下していた状態から、ベリーフライと呼ばれる伏せの状態で手足を伸ばした落下抵抗の大きな姿勢を取りましょう。この姿勢なら、落下速度を時速200キロメートル程度まで減速することができます。
この時点では、地上までおよそ2分の猶予があるので、着地したときに少しでも生存確率が高くなる場所を探すことをオススメします。
これまでに上空から自由落下して生き延びた人の多くは、干し草の山や茂みなどがクッションとなったことで生還を果たしています。同じ理由で雪原や沼地も着地場所として候補に上がります。
反対に海や湖といった液体は、瞬時に変形しないため、高速で衝突すると個体にぶつかるのと同じことが起こります。つまり、水面に落ちることは地面にそのままぶつかることと変わらないため、オススメできません。
さあ、クッション性のあるものは探せましたか?あまり時間はありませんよ。
高度が600メートルになると、いよいよ着地までに残された時間は10秒余りとなります。この段階でできることは、生存を祈ることと着地の姿勢を取ることくらいでしょう。1963年に発行された連邦航空庁の文章では、「脚を揃えて、かかとを上空に向けて、膝を抱えることで生存率が上がる」と報告されています。
また、着水する場合には足から入水する方法が有効です。転落死の死因で最も多いのは頭蓋の損傷によるものなので、頭部へのダメージが最小限になるよう努力することが肝要です。
そしてついに高度0メートル。
3分間の自由落下を経て、地上に衝突します。もし、幸運にも生還できた場合、周囲の状況を確認しましょう。人里からそう遠くない牧草地なら、生存の喜びを噛み締めてそのまま救助を待っていれば大丈夫です。
しかし、ジャングルや砂漠、雪原など新たな生存戦略が必要な場所に着地した場合には…生き残るための第二ラウンドが始まることを覚悟しましょう。
実際に、ユリアナ・ケプアという少女は、1971年に航空機事故でペルーの密林に墜落しました。ただ一人の生存者だった彼女は、ジャングルを自力で抜けて、生きながらえています。この実話は『奇跡の詩』として、1974年に映画化もされていますので興味がある方はそちらも是非。
とはいえ、米国家運輸安全委員会の調査によれば、航空機事故で死亡する確率は0.0009%。これからも安心して空の旅を楽しみましょう。落下した場合は、落下中にこの動画を見れば…時間と足りなさそうです。